 9月7日(日)、有楽町の東京国際フォーラムにて2014年度第2回赤坂会例会が行われました。今回のテーマは「The Treatment Planning Sessions」。あいにくの空模様でしたが全国から100名を超える方々が集まりました。
9月7日(日)、有楽町の東京国際フォーラムにて2014年度第2回赤坂会例会が行われました。今回のテーマは「The Treatment Planning Sessions」。あいにくの空模様でしたが全国から100名を超える方々が集まりました。
会長である野寺先生の挨拶後、顧問である寺西先生より、今回のテーマであるトリートメントプランニングの概要についてご説明がありました。近年、世界の学会で多く採用されるに至った歴史的背景や診断は1つであるが治療方法は無数でありそれをディスカッションすることの重要性をお話しになりました。その後プログラムチェアマンである高田先生より演者の紹介がありセッションに移っていきました。今回は、Dr3名(矯正医を1人含む)、DT.1名、DH.1名というチーム編成で若手チーム、東北チーム、ベテランチームという3チームが担当医よりあらかじめ用意された基礎資料を基に治療計画を立案し、ディスカッションしていきました。
 まず、トリートメントプランニングセッションにおける症例発表者の佐藤博宣先生より、基礎資料の提示があり、若手チーム(DR加部、DR小木曽、DR川崎、DT平野、DH鈴木)、東北チーム(DR藤野、DR工藤、DR水川、DT菅原、DH高橋)、ベテランチーム(DR中丸、DR高田、DR野寺、DT岩渕、DH伊藤)がそれぞれ診断や治療計画を発表されました。
まず、トリートメントプランニングセッションにおける症例発表者の佐藤博宣先生より、基礎資料の提示があり、若手チーム(DR加部、DR小木曽、DR川崎、DT平野、DH鈴木)、東北チーム(DR藤野、DR工藤、DR水川、DT菅原、DH高橋)、ベテランチーム(DR中丸、DR高田、DR野寺、DT岩渕、DH伊藤)がそれぞれ診断や治療計画を発表されました。 今回のケースでは、アンテリアガイダンスをいかに獲得するかや、初診時にすでに不適切な位置に埋入されてしまっているインプラントへの対応、予後が不安視される歯牙へのアプローチ等、ポイントが多岐にわたりましたが、三者三様のアプローチがありそれゆえにディスカッションは尽きませんでした。会場からも矯正が必要か否かの疑問や、補綴設計についても多くの質問がなされ、発表者の方々もご自身の考えの経緯を説明しながら熱い議論が繰り広げられました。また補綴物の形態や清掃性をめぐってはテクニシャンやハイジニストの方からも意見が寄せられました。
今回のケースでは、アンテリアガイダンスをいかに獲得するかや、初診時にすでに不適切な位置に埋入されてしまっているインプラントへの対応、予後が不安視される歯牙へのアプローチ等、ポイントが多岐にわたりましたが、三者三様のアプローチがありそれゆえにディスカッションは尽きませんでした。会場からも矯正が必要か否かの疑問や、補綴設計についても多くの質問がなされ、発表者の方々もご自身の考えの経緯を説明しながら熱い議論が繰り広げられました。また補綴物の形態や清掃性をめぐってはテクニシャンやハイジニストの方からも意見が寄せられました。 3チームの発表後は、佐藤先生が実際なさった治療方針や最終補綴物までの流れを時系列に沿って発表されました。前述の3チームがそれぞれ理想と思われるプランニングを出された後の発表は大変やりづらかったと思いますが、フルマウスリコンストラクションを丁寧に仕上げており、大変勉強になりました。その後歯周外科や小矯正についてディスカッションとなり、熱を帯びたまま午前のトリートメントプランニングセッションが終了しました。会場の多数決により東北チームの発表がアワードとなり、後の懇親会で表彰となりました。
3チームの発表後は、佐藤先生が実際なさった治療方針や最終補綴物までの流れを時系列に沿って発表されました。前述の3チームがそれぞれ理想と思われるプランニングを出された後の発表は大変やりづらかったと思いますが、フルマウスリコンストラクションを丁寧に仕上げており、大変勉強になりました。その後歯周外科や小矯正についてディスカッションとなり、熱を帯びたまま午前のトリートメントプランニングセッションが終了しました。会場の多数決により東北チームの発表がアワードとなり、後の懇親会で表彰となりました。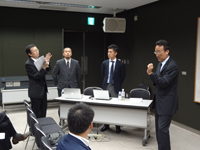 昼食をはさみ午後は会員発表に移りました。テーマは"ラボコミニュケーション"。トップバッターはよしだ歯科クリニック勤務の小森正樹先生とetu-pirika Dental Art開業の平野直樹さんで「欠損に対しインプラントを用い、上下臼歯部をクラウンブリッジにより修復した症例」と題し発表されました。初期治療の段階から診断用Wax upやプロビジョナルレストレーション作成時にラボコニミュケーションをはかり進められていました。実際のwax upにより補綴範囲の拡大がなされており、緊密な咬合を必要とする臼歯部補綴の際には必要なステップであると改めて感じました。また、初期治療によって炎症のコントロールがきちんとなされている点も印象的でした。
昼食をはさみ午後は会員発表に移りました。テーマは"ラボコミニュケーション"。トップバッターはよしだ歯科クリニック勤務の小森正樹先生とetu-pirika Dental Art開業の平野直樹さんで「欠損に対しインプラントを用い、上下臼歯部をクラウンブリッジにより修復した症例」と題し発表されました。初期治療の段階から診断用Wax upやプロビジョナルレストレーション作成時にラボコニミュケーションをはかり進められていました。実際のwax upにより補綴範囲の拡大がなされており、緊密な咬合を必要とする臼歯部補綴の際には必要なステップであると改めて感じました。また、初期治療によって炎症のコントロールがきちんとなされている点も印象的でした。 続いて、エド日本橋歯科勤務の吉田雄太先生とファインデンタルアート開業の小林正直さんが「遊離端欠損に対して咬合再構成を行った症例」と題し発表されました。咬合再構成においてラボコミニュケーションは必須であり、プロビジョナル作製時にいかに口腔内の情報をラボサイドに伝えるかやプロビジョナルで得られた情報をいかに最終補綴物に反映していくかという点が肝要であり、大変参考となるケースでした。特に前歯部の形態に焦点があてられており、ご自身の反省等もふまえた発表でした。
続いて、エド日本橋歯科勤務の吉田雄太先生とファインデンタルアート開業の小林正直さんが「遊離端欠損に対して咬合再構成を行った症例」と題し発表されました。咬合再構成においてラボコミニュケーションは必須であり、プロビジョナル作製時にいかに口腔内の情報をラボサイドに伝えるかやプロビジョナルで得られた情報をいかに最終補綴物に反映していくかという点が肝要であり、大変参考となるケースでした。特に前歯部の形態に焦点があてられており、ご自身の反省等もふまえた発表でした。 最後に、寺西歯科勤務の三宅甲太郎先生と同じく寺西歯科勤務の石毛秀和さんによる、「欠損補綴にR.P.D.とImplantを用いた1症例」と題し発表されました。トリートメントデンチャーやファイナルのR.P.D.作製時写真も多くみられ、大変勉強になりました。お互いにリジットなR.P.D.の経験が浅いとのことで、1つ1つの過程での苦慮した点など率直に発表されており、今後の参考にさせて頂きたいと思いました。発表後のディスカッションでは会場からレストシートの光沢具合やプラーク付着状態によって推測出来ることのご教授があり改めて臨床の奥深さを知ることが出来ました。
最後に、寺西歯科勤務の三宅甲太郎先生と同じく寺西歯科勤務の石毛秀和さんによる、「欠損補綴にR.P.D.とImplantを用いた1症例」と題し発表されました。トリートメントデンチャーやファイナルのR.P.D.作製時写真も多くみられ、大変勉強になりました。お互いにリジットなR.P.D.の経験が浅いとのことで、1つ1つの過程での苦慮した点など率直に発表されており、今後の参考にさせて頂きたいと思いました。発表後のディスカッションでは会場からレストシートの光沢具合やプラーク付着状態によって推測出来ることのご教授があり改めて臨床の奥深さを知ることが出来ました。 今回の例会ではトリートメントプランニングや会員発表を通じ、診査データの見方や診断へつなげるプロセスを事細かに学ぶことが出来、明日からの臨床に生きる大変有意義な例会であったと感じました。
今回の例会ではトリートメントプランニングや会員発表を通じ、診査データの見方や診断へつなげるプロセスを事細かに学ぶことが出来、明日からの臨床に生きる大変有意義な例会であったと感じました。 根間 大地




