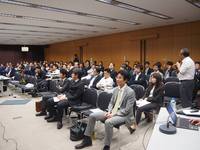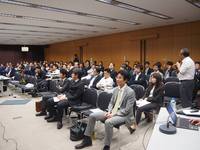5月17日(日)、東京国際フォーラムにて2015年度赤坂会第1回例会が行われました。
今回のテーマは「補綴前処置としてのペリオドンタルティッシュマネージメント」
高田新会長の初陣にふさわしい快晴の中、全国から90名以上の方々が集まりました。

まず、高田新会長の会長決意表明も兼ねたプレゼンテーションから始まりました。今後の赤坂会のテーマとして掲げられた 1)Casting 2)Science 3)Globalizationの必要性や本年度のスローガンである「吠えろ」のご説明の後、今回の例会テーマである「補綴前処置としてのペリオドンタルティッシュマネージメント」について参考症例を交えながら趣旨説明をしていただきました。その後顧問の寺西先生よりご挨拶があり、基調講演へと移っていきました。

基調講演は長らくJIADSで講師をお勤めの宮前守寛先生で、例会テーマと同じく「補綴前処置としてのペリオドンタルティッシュマネージメント」という演題での講演でした。抑えるべきベーシックな所からアドバンスな内容までご自身の症例を交えながら非常に解りやすくかつ示唆に富んだ素晴らしいご講演でした。最終修復物を審美的に仕上げるためには歯周疾患や縁下カリエス、歯牙の位置異常等の問題を解決し清掃性に優れた安定性の高い歯周組織を構築する必要があります。そのための診断の一助となる様々な分類(歯肉、骨、歯間距離等)や診断結果から導き出される適切な術式(切除療法、再生療法、矯正治療等)の選択をご自身の症例や文献を通して理路整然とまとめておられて、講演中どんどん頭の中が整理されていく爽快感が絶えませんでした。やはり結果を残される先生ほど、基本を忠実に守り、理論に基づいた診査診断や術式の選択を確実に行っていることを改めて認識し背筋の伸びる思いでした。後半はインプラント周囲組織への角化歯肉の必要性についての具体的な講義もあり、こちらも改めてインプラント周囲組織への配慮も学ばせて頂きました。ご講演後、会場から質問やそれに基づくディスカッションも行われ、熱を帯びたまま午前は終了となりました。
お昼休憩をはさみ午後は3名の会員発表へと移っていきました。

トップバッターは高田新会長自ら「結合組織移植による根面被覆を行ったフルマウスリコンストラクションケース」との演題で発表されました。元々の不良修復物が多く、天然歯もリセッションを伴い全額的な治療が必要な難しいケースでしたが、一つ一つの診査や術式を丁寧にまとめられ、ファイナルも非常にきれいでした。ご自身の経験を基に根面被覆の際の留意した点やインプラント周囲組織への考察についても大変勉強になりました。会場からも根面被覆後のプロビジョナルへの移行時期やマージンの設定について等テーマに即した質問も飛び交いました。

続いて、内田歯科医院勤務の加部先生の発表に移りました。演題は「デンチャースペース確保のためのクラウンレングスを行ったオーバーデンチャーの症例」。本ケースは私自身、若手合宿、福岡ジョイントと合わせて3回目の拝聴となりましたが今回はデンチャースペースの確保のために行った歯周外科にフォーカスを絞ったプレゼンテーションでした。最終補綴物の破折のリスクを軽減するための適正な厚みの確保やそこから逆算して歯牙や骨の削除量を求めてオペに当たる必要性などご自身の反省や考察も含めた発表でした。ディスカッションでは治療計画について他に選択肢がなかったのか、上下歯列の位置関係の考察について等診査診断にこだわる赤坂会らしい議論におのずと発展していきました。

最後は、愛知県にてご開業の田ケ原先生による発表で演題は「矯正治療と歯肉粘膜処置を行ったインプラント症例の経過報告」。初診が15年以上前のフルマウスリコンストラクションのケースで治療中や治療後の経過についても時系列に沿ってご発表頂きました。
治療が大掛かりになればなるほど、思いもよらぬことも起こりうると思いますが、その都度考察とフォローアップをされておりケースの壮大さを感じました。また時代と共に治療オプションが増えるため、治療当初は選択肢になかったことにも対応出来るよう知識のアップデートを怠らない姿勢が大切であると改めて学ばせて頂きました。ディスカッションでは抜歯基準や外科術式についての質問から矯正や顎関節の状態などを含めた診断について議論が尽きず、熱を帯びたまま閉会となりました。
今回改めて、永続性の高い補綴治療に際し診査診断の大切さとそれに伴う治療術式の選択、また治療を遂行できるスキルの必要性等、研鑽の積み重ねの大切さを痛感する大変有意義な一日となりました。
根間 大地