2017年7月16日に沖縄県市町村自治会館にて第3回環太平洋インプラントフォーラム(Pacific Rim Implant Forum;PRIF)が開催されました。今年は「これからのインプラントと補綴戦略」というテーマでした。

発表はアメリカから
Dr.Jeffery W.Johnston 「Implant Complications:Prevention and Treatment」
韓国からは
Dr. Lee Jong Hyuk 「Strategy of soft tissue graft in anterior teeth restoration using dental implant」
日本からは Club WESPICから
Dr.Taichi Kamishita 「インプラント周囲のSoftTissue Mnagement のタイミングとその要点」
北九州歯学研究会から
Dr.Yasuharu Kai 「インプラント治療成功のための歯列改善への試み」
I.O.Rから
Dr.Takashi Kodama 「BMP-2を応用した骨誘導性インプラントの可能性に迫る」
5-Dからは
Dr.Tsutomu Tanno 「Orthodontic Implant site development using labial root torque」
そして赤坂会より
Dr.Akinari Kabe「歯冠形態の修正でアンテリアガイダンスを改善し、右上欠損部をインプラントで対応した症例」でした。
発表は全て英語で行われ、今年も質疑応答は梅津清隆先生の通訳のもと行われました。




今回のテーマは「これからのインプラントと補綴戦略」ということで幅広いテーマでしたが、骨誘導性インプラントの可能性、インプラント前処置として矯正治療や、骨造成、軟組織移植、そしてインプラント周囲炎など様々な発表をしていただき、非常に盛り上がったディスカッションとなりました。
また前日のウェルカムパーティーでは寺西先生を筆頭にPRIFのメンバーが沖縄で釣り上げた魚が提供され、新鮮なまま美味しくいただくことができました。


GARAパーティーはリッチモンド那覇のテラスブルーオキナワで行われ、夜遅くまで盛大に盛り上がり、2017年度PRIFは終了となりました。

大会長である友寄先生、実行委員長の飯沼先生、海外より演者としてそしてお忙しい中、ご準備頂いた先生方に感謝申し上げます。
来年2018年7月1日 第4回PRIFもよろしくお願いいたします。
内田歯科医院 吉武 秀

























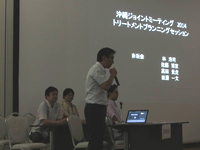







































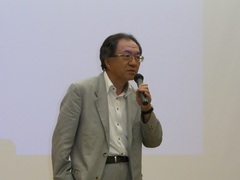










 7月17日日曜日、赤坂会・KIDS・Club WESPIC合同症例検討会が那覇市自治会館にて開催されました。今年は福岡から榊恭範先生が顧問をされているKIDSも参加いただき、初めて3つのスタディグループのジョイントミーティングとあって、参加人数も多く、前日の懇親会から盛りあがりをみせていました。そして当日はどのケースもそれぞれのスタディーグループの個性を踏まえた臨床ケースに、熱いディスカッションが行われました。
7月17日日曜日、赤坂会・KIDS・Club WESPIC合同症例検討会が那覇市自治会館にて開催されました。今年は福岡から榊恭範先生が顧問をされているKIDSも参加いただき、初めて3つのスタディグループのジョイントミーティングとあって、参加人数も多く、前日の懇親会から盛りあがりをみせていました。そして当日はどのケースもそれぞれのスタディーグループの個性を踏まえた臨床ケースに、熱いディスカッションが行われました。 2ケース目はWESPICから宇根先生が「L.O.T.、IOD、ショートインプラントを応用した咬合崩壊症例」を発表されました。片側性の残存歯を保存されることにご苦労なさったケースで、今後の予後にディスカッションが交わされました。またアストラテックのOsseo Speedを用いたケースであり議論を呼びました。
2ケース目はWESPICから宇根先生が「L.O.T.、IOD、ショートインプラントを応用した咬合崩壊症例」を発表されました。片側性の残存歯を保存されることにご苦労なさったケースで、今後の予後にディスカッションが交わされました。またアストラテックのOsseo Speedを用いたケースであり議論を呼びました。 榊先生に中締めを頂き昼食をはさみ、午後からは樋口琢善先生から「補綴物のマージンを歯肉縁下に設定する際の要件」を発表されました。日々臨床で直面する補綴マージンのテーマに、ディスカッションが尽きませんでした。
榊先生に中締めを頂き昼食をはさみ、午後からは樋口琢善先生から「補綴物のマージンを歯肉縁下に設定する際の要件」を発表されました。日々臨床で直面する補綴マージンのテーマに、ディスカッションが尽きませんでした。 最後は赤坂会会長吉田拓志先生が「多数歯カリエスを伴った臼歯部咬合崩壊症例に対し、インプラントにより咬合支持を得た症例」を発表されました。Ⅱ級で欠損も多い厳しいケースでしたが、吉田先生らしいL.O.T.やグラフトを交え細部に配慮された診療にとても勉強になりました。
最後は赤坂会会長吉田拓志先生が「多数歯カリエスを伴った臼歯部咬合崩壊症例に対し、インプラントにより咬合支持を得た症例」を発表されました。Ⅱ級で欠損も多い厳しいケースでしたが、吉田先生らしいL.O.T.やグラフトを交え細部に配慮された診療にとても勉強になりました。








