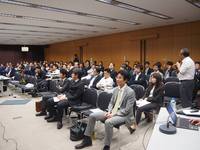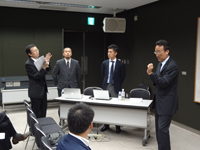11月26日に東京国際フォーラムにて、スタディーグループ赤坂会忘年特別講演会が開催されました。今回の基調講演は5-D Japanファウンダーの船登彰芳先生にお越しいただき、『なぎさ歯科クリニックの軌跡-歯周・インプラントに特化した医院として』という題でご講演していただきました。 講演は歯周治療、インプラント治療だけでなく、包括的に行った症例まで論文などのエビデンスも混ぜながら多数見させていただき、非常に勉強になりました。 また船登先生の過去から現在に至るまでの臨床に対する考え方の変化はとても考えさせられるもので、私のような若手にとって非常にためになるお話だったと思います。 特に印象に残っているのは天然歯をできる限り保存し削りたくないと現在は考えているということでした。しかし、削らなければならないときは削るし、抜かなければいかないときは抜くとはっきりとおっしゃっていました。そこには、赤坂会も大切にしている診査、診断があると思います。ただ、私のような若手にとってはまだまだその見極めが難しく、日々診査診断を行いながら悩んでおりますが、今後自信をもって診断できるよう引き続き頑張っていきたいと思いました。
赤坂会からの会員発表は今年のテーマであった伝承の締めにふさわしく、赤坂会を代表とする先生方の中から吉田拓志先生の『臼歯部咬合崩壊を伴った慢性歯周炎患者に包括的な治療を行った一症例』、新藤有道先生の『Root submergence technique を応用した症例』、飯沼学先生の『インプラントをパーシャルデンチャーの支台歯として用いて機能回復を試みた症例』の発表でした。 どの症例もそれぞれの先生の特徴がある発表で若手にとって非常に勉強になりました。しかし、ディスカッションの時間がほとんどなかったので、ディスカッションの活発な赤坂会の先生方にとっては少し不完全燃焼だったのかもしれませんが、有意義な時間となりました。
懇親会は会場を変え東京TOKIAビルのP.C.M.にて行われました。他のスタディーグループの先生方にもお越しいただき、そして毎年恒例の抽選でも数多くの景品が協賛企業から提供されました。余興は加部先生、根間先生、田中先生、得居先生による体を張った派手なダンスショーで非常に盛り上がりました。
また、今年のアワードは
Terry's award Dr.川崎宏一郎でした。
Akasaka award Dt.伊藤和明
新人賞 Dr.吉武秀
おめでとうございます。
内田歯科医院 吉武 秀